誘電関数の第一原理計算:各種材料の解析事例#
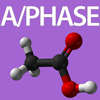
誘電関数は、物質が外部電場にどう応答するかを記述する基本的な物理量であり、コンデンサ材料や光デバイス、半導体技術など、幅広い分野で極めて重要です。この物性値は、電子の分極に由来する「電子系」の寄与と、電場によるイオン(原子核)の変位に由来する「格子系」の寄与の和として表されます。本解析では、第一原理計算ソフトウェアAdvance/PHASEを用い、代表的な機能性材料の誘電関数を計算し、その予測精度を実証します。
Keywords: 第一原理計算, DFTシミュレーション, 誘電関数, ベリー位相, ボルン有効電荷, 格子振動
計算手法#
Advance/PHASEでは、周波数依存の誘電関数の第一原理計算が可能です。実験結果と比較するため、ここでは静的な誘電関数(誘電率)に着目します。 は、電子分極による寄与である高周波誘電率 と、格子振動(フォノン)を介したイオン変位による格子誘電率 の和で与えられます。
- 電子系誘電率 (): 自己無撞着場(SCF)計算で得られた電子状態から、電子だけの誘電応答を計算します。高周波誘電率 は、原子核(イオン)が追随できないような高周波領域(可視光など)における電子の分極率を指します。この領域では電子の応答が周波数にあまり依存しなくなるため、計算上は電子だけの誘電関数を求め、そのゼロ周波数極限()を取ることでこの値を決定します。
- 格子系誘電率 (): 格子振動解析と、現代的な分極理論であるベリー位相(Berry Phase)法に基づくボルン有効電荷 () の計算結果を組み合わせて求められます。この一連の計算はワークフロー構築によりスムーズに実行できます。
主な計算条件#
本解析における計算条件は下記のように設定されています。
- 擬ポテンシャル: ウルトラソフト型、またはノルム保存型擬ポテンシャル
- 交換相関汎関数: GGA-PBE
- 波動関数のカットオフエネルギー: 25 Rydberg
- k点サンプリング: 各結晶の性質に応じて設定(例:GaNでは6×6×3、SiO2では4×4×4)
計算結果:ボルン有効電荷と誘電率#
ボルン有効電荷#
ボルン有効電荷は、原子の変位がどれだけの分極を生み出すかを示すテンソル量です。公称価数(例: Si4+, O2-)とは異なり、原子が動いた際の周りの電子雲の追随(動的電荷移動)の効果を含んだ量であり、格子系誘電率の大きさを決定する上で本質的です。
1. α-SiO2 (石英)#
Si原子のボルン電荷は約+3から+3.5程度となり、O原子は約-1.5から-2程度となり、公称価数(Si4+, O2-)よりも絶対値が小さいことが分かります。これは、強い共有結合性を反映しています。以下は代表的なSi原子、O原子の計算結果を示します。
2. 窒化物半導体: AlN と GaN#
これらの材料では、ボルン電荷の絶対値が公称価数(例: Ga3+, N3-)に近くなる傾向がありますが、それでも価数そのものではないことが重要です。異方性(xx成分とzz成分の違い)も見られます。
3. 酸化物半導体: ZnO#
計算されたZn原子のボルン有効電荷の絶対値(~2.15–2.20)は、Zn2+の公称価数(2+)に近いものの、それをわずかに上回っています。これは結合の強いイオン性を反映しつつも、共有結合性に由来する動的な電荷移動の効果が含まれていることを示唆します。このように、原子変位に伴う周囲の電子雲の再配分により、ボルン有効電荷が公称価数を大きく超える現象は「異常ボルン電荷 (Anomalous Born effective charge)」として知られ、電荷の非局在性を反映したものです。また、xx成分(2.15)とzz成分(2.20)の間にはわずかな異方性も見られます。
4. 強誘電体: LiTaO3#
強誘電体では、少なくとも一つの原子が非常に大きなボルン有効電荷を持つことが特徴です。LiTaO3では、Taのボルン電荷が+7を超えており、これが巨大な格子系誘電率の起源となっています。以下は代表的なLi原子、Ta原子の計算結果を示します。
誘電率の計算結果と考察#
表1a. c軸垂直方向(c, xx)の誘電率
| 材料 | 電子系 () | 格子系 () | 合計 () | 実験値 |
|---|---|---|---|---|
| α-SiO₂ | 2.34 | 2.34 | 4.68 | ~4.5 |
| AlN | 4.46 | 3.70 | 8.16 | ~8.5 |
| GaN | 5.19 | 3.53 | 8.72 | ~9.5 |
| ZnO | 4.13 | 5.17 | 9.30 | ~7.8 |
| LiTaO₃ | 4.44 | 40.11 | 44.55 | ~41-43.5 |
表1b. c軸平行方向(c, zz)の誘電率
| 材料 | 電子系 () | 格子系 () | 合計 () | 実験値 |
|---|---|---|---|---|
| α-SiO₂ | 2.35 | 2.41 | 4.76 | ~4.5 |
| AlN | 4.60 | 4.93 | 9.53 | ~10 |
| GaN | 5.46 | 6.07 | 11.53 | ~10.4 |
| ZnO | 4.35 | 6.67 | 11.02 | ~8.9 |
| LiTaO₃ | 4.33 | 40.31 | 44.64 | ~40-44.5 |
上の表は、Advance/PHASEによる誘電率の計算結果が、多様な材料系において実験値 [1-5] と概ね良好な一致を示しています。特に強誘電体LiTaO3の巨大な誘電率も精度良く再現できています。一方で、ZnOにおいては実験値に対してかなりの過大評価をする結果となりました。この乖離は、計算に用いた交換相関汎関数(GGA-PBE)が半導体のバンドギャップを過小評価することに起因し、その結果として電子系の誘電率()を過大評価する傾向があるためと考えられます。この結果から、さらに踏み込んだ考察が可能です。
- 物性の起源の解明: 合計値だけを見るのではなく、誘電率を電子系()と格子系()の寄与に分離することで、その材料の誘電特性が何に由来するのかを理解できます。例えば、LiTaO3の高い誘電率は、電子分極ではなく格子分極が支配的であることを明確に示しています。格子系の寄与(40)は電子系の寄与(4.4)の約10倍であり、これは先に示したTa原子の巨大なボルン有効電荷と直接結びついています。
- 材料クラスごとの特徴:
- SiO2のような典型的な絶縁体では、電子系と格子系の寄与はほぼ同程度です。
- AlN, GaN, ZnOといった重要な半導体材料では、格子系の寄与が電子系のそれを上回ることもあり、正確な物性予測には格子振動の取り扱いが不可欠であることがわかります。
- LiTaO3のような強誘電体・圧電体材料では、格子系の寄与が桁違いに大きくなります。これは特定の格子振動モード(ソフトモード)と大きなボルン有効電荷が結合し、外部電場に対して極めて大きな分極応答を生み出すためです。
- 異方性の再現性: AlNやGaNのような六方晶の材料では、c軸方向(zz)とそれに垂直な方向(xx, yy)で誘電率が異なります。本計算は、この異方性を正しく再現しており、実験値の傾向ともよく一致しています。
まとめ#
本解析では、第一原理計算ソフトウェアAdvance/PHASEを用い、各種機能性材料(SiO2, AlN, GaN, ZnO, LiTaO3)の静誘電率を算出しました。物質の誘電率は、電場に対する電子の応答(電子系寄与)と、原子核(イオン)の応答(格子系寄与)の和で表されます。原子の動的な応答を示すボルン有効電荷の計算から、LiTaO3のような強誘電体では、特定の原子が公称価数を大幅に超える巨大なボルン有効電荷を持つことが、その高い誘電率の起源であることが明らかになりました。計算された各種材料の誘電率は、実験値と良好な一致を示し、本手法が材料設計において強力な予測ツールであることを実証しています。
本解析の詳細や、研究への適用可能性に関するご相談はこちら
お問い合わせ参考文献#
- A. R. von Hippel, Dielectric Materials and Applications, John Wiley and Sons (1954).
- A. T. Collins, E. C. Lightowlers, and P. J. Dean, "Lattice vibration spectra of aluminum nitride", Phys. Rev. 158, 833 (1967).
- A. S. Barker, Jr. and M. Ilegems, "Infrared lattice vibrations and free-electron dispersion in GaN", Phys. Rev. B 7, 743 (1973).
- H. Yoshikawa and S. Adachi, "Optical Constants of ZnO", Jpn. J. Appl. Phys. 36, 6237 (1997).
- A. M. Glass, "Dielectric, thermal, and pyroelectric properties of ferroelectric LiTaO3", Phys. Rev. 172, 564 (1968).
- A. S. Barker Jr, A. A. Ballman, and J. A. Ditzenberger, "Infrared study of the lattice vibrations in LiTaO3", Phys. Rev. B 2, 4233 (1970).
関連ページ#
- 第一原理計算ソフトウェア Advance/PHASE
- 解析分野:ナノ・バイオ
- 産業分野:材料・化学